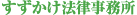例)離婚原因、子どもの親権、養育費、財産分与、慰謝料、DV・ストーカー被害等
Q1.婚姻費用
まだ離婚はしていませんが、離婚を前提に、夫と別居しています。
夫婦の間には未成年の子どもがいます。子どもは、私と一緒に生活しています。
別居中の夫に、私と子どもの生活費を請求できますか。
A.
夫婦が別居していても、婚姻している間は、生活費(法律用語で「婚姻費用」といいます)を請求できます。
請求できる金額は、夫と妻の各収入金額、子どもの年齢や人数などの事情に応じて決まります。
東京家庭裁判所の参考資料「養育費・婚姻費用算定表」が一応の目安になるでしょう。
ただし、個別の事情(例えば、住宅ローン、私立学校の学費など)により、算定表の金額どおりにならないケースもあります。
Q2.離婚時の合意
離婚しようと思っています。離婚するときには、どのような取り決めをする必要がありますか。
なお、夫婦の間には、未成年の子どもがいます。
A.
離婚するときは、①財産分与、②慰謝料について、取り決めをします。これに加えて、③年金分割の取り決めをすることもあります。
さらに、未成年の子どもがいるときには、④子どもの親権者、⑤養育費、⑥子どもとの面接交流についても、取り決めをします。
Q3.財産分与の対象(1)対象となる財産
財産分与の対象になる財産には、どのようなものがありますか。
預貯金や有価証券のほか、不動産、自動車、リゾート会員権なども、財産分与の対象になりますか。
A.
財産分与では、別居時を基準として、「夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産」を分与します。
「夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産」であれば、預貯金や有価証券のほか、不動産、自動車、リゾート会員権、家財道具なども、財産分与の対象となります。
Q4.財産分与の対象(2)単独名義の財産
財産分与では、夫婦共有名義の財産だけではなく、夫婦どちらか一方の単独名義の財産も、財産分与の対象になりますか。
A.
夫婦共有名義になっていなくても、「夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産」であれば、潜在的に夫婦共有であるとみなされます。
したがって、夫婦どちらかの単独名義でも、財産分与の対象になります。
Q5.財産分与の対象(3)相続財産
妻から、財産分与として「自宅不動産の半分」を要求されました。
この自宅不動産は、私が亡父親から相続した物件です。親から相続した不動産でも、財産分与の対象になりますか。
A.
離婚に伴う財産分与は、「夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産」を分与するものです。
親から相続した財産は、「夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産」ではありませんので、財産分与の対象にはなりません。
Q6.財産分与の割合
財産分与の割合について、基準や目安はありますか。
A.
財産分与の割合は、昨今では、夫婦2分の1ずつが基本です(2分の1ルール)。
ただし、分与割合を決めるときには、共同財産の形成に対する貢献度を考慮に入れますので、貢献度が明らかであるような個別事情があるときには、調整(増減額)を行い、2分の1ずつにならないケースもあります。
また、離婚による弱者に対する扶養的な要素、慰謝料的な要素を考慮して、多少の調整を行うこともあります。
Q7.離婚に伴う慰謝料
離婚のときは、かならず慰謝料を請求できますか。
私たちの離婚は、相手方の不倫や暴力のような、はっきりした離婚原因がある訳ではなく、いわゆる性格の不一致による離婚です。
A.
慰謝料請求が認められるためには、相手方の不貞、暴力、虐待などの「有責」行為がなければなりません。
相手方にこれといった有責行為があるわけではなく、単なる性格の不一致で離婚するときには、原則として、慰謝料は請求できません。
Q8.養育費(1)基準と期間
離婚にあたり、子どもの親権者を私にする予定です。
子どもの養育費を相手方に請求しようと思いますが、養育費の金額に基準はありますか。
また、養育費は、いつまで支払ってもらえますか。
A.
養育費の金額は、夫と妻の各収入金額、子どもの人数や年齢などの事情に応じて決まります。
東京家庭裁判所の参考資料「養育費・婚姻費用算定表」が一応の目安になるでしょう。ただし、個別の事情(例えば、再婚、住宅ローン、私立学校の学費など)により、算定表の金額どおりにならないケースもあります。養育費の支払いは、子どもの成人(20歳)までとすることが多いですが、子どもの大学卒業までとするケースも、よく見られます。
Q9.養育費(2)一括請求の可否
離婚にあたり、私が子どもの親権者になる予定で、相手方と養育費の話し合いをしています。
相手方は、養育費を毎月支払うと言っています。でも、私としては、不安ですので、離婚時に養育費全額を一括払いしてもらいたいです。
養育費の全額一括払いを求めることはできますか。
A.
養育費の全額一括払いの請求はできません。
毎月払いが原則です。子どもの生活費という性質上、毎月払いで十分だからです。
Q10.養育費(3)夫婦とも収入があるとき
離婚にあたり、子どもの親権者を妻にするという取り決めをすることになりました。
妻は、フルタイムで仕事をしており、それなりの収入を得ています。
妻にそれなりの収入があっても、夫は、子どもの養育費を支払わなければならないのですか。
A.
妻に収入があっても、夫にも収入があれば、養育費を支払わなければなりません。
ただし、夫婦の各収入金額により、支払うべき養育費の金額は変わります。東京家庭裁判所の参考資料「養育費・婚姻費用算定表」が一応の目安になるでしょう。
また、Q8もご覧下さい。
Q11.面会交流(面接交渉)
妻と離婚することになりました。
妻は、子どもの親権を主張し、「離婚した後は、あなたには、子どもに会わせたくない」と言い張ります。
私は、子どもの親権者は妻でもよいと思っていますが、離婚した後も、子どもと定期的に会いたいです。
妻が拒否している場合でも、子どもとの面会は認められますか。
A.
離婚後、親権者にならない親であっても、子どもに個人的に面会したり文通したりすることができます。
これを「面会交流(面接交渉)」といいます。
ただし、面接交流で、もっとも重視されるのは、親の気持ちではなく、「子の福祉」です。
そのため、面接交流が子の福祉を害するような事情(典型例としては、子に対する暴力・虐待)があるときには、制約を受けます。
また、面会できるといっても、いつでも自由に会えるとは限りません。
面接交流の条件(面接の頻度や時間)について、取り決め(例えば、「毎月1回」など)をすることが多いです。
Q12.離婚後の配偶者の生活費請求の可否
夫と離婚することになりました。
私は、これまで専業主婦をしており、結婚してから仕事をした経験はありません。
離婚した後も、夫に、私の生活費を支払ってもらうことはできますか。
A.
離婚後は、夫に、妻の生活費を請求することはできません。
子どもがいる場合は、養育費を請求することはできますが、養育費は、子どもの生活費であって、妻の生活費ではありません。
離婚後の生活設計・経済的自立については、離婚する前から、情報を収集し、計画を立てておく必要があります。